当社はCookieを使用して、お客様が当社のWebサイトでより良い体験を得られるようにしています。引き続き閲覧する場合は、当社グループのプライバシーポリシー に同意したことになります。
早稲田大学 先進理工学研究科 応用化学専攻
三瓶大志 様(写真右側)
七種紘規 様(写真左側)
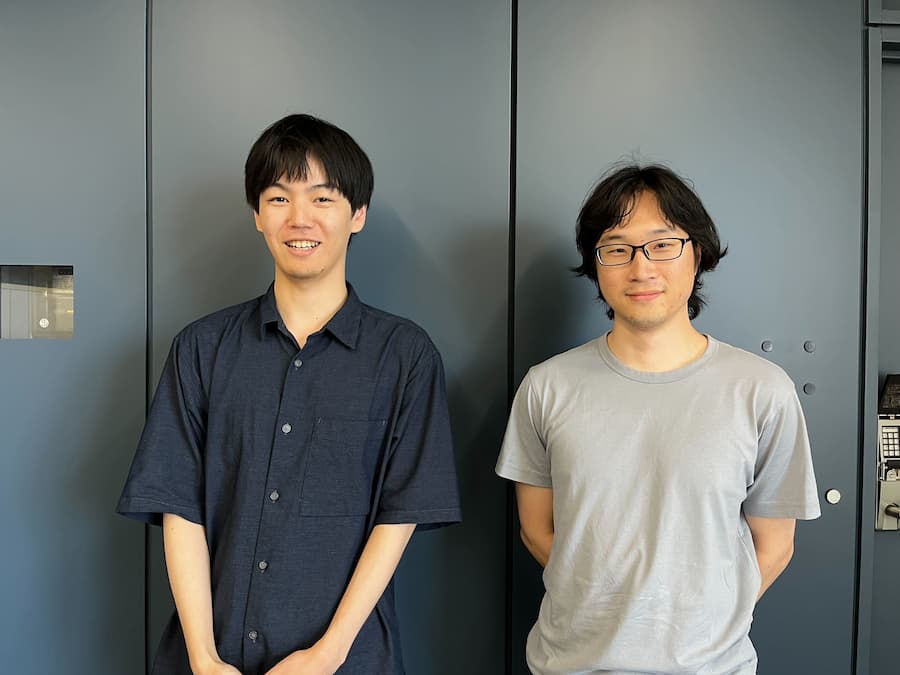

2023年度の未踏ターゲット事業では、合金触媒の結晶構造において最も安定な金属配置を量子アニーリング・イジングマシンを使って探索するソフトウェアの開発に取り組みました。一定の成果は出たものの、触媒反応は結晶構造全体というよりも「表面」で起こる現象であるため、表面に着目した場合の最適な金属配置を知りたいという新たな課題を発見しました。そこで、2024年度の未踏ターゲット事業では、表面における金属原子の最適な配置を探索するソフトウェアと、その利用を支援するためのドキュメントの開発に取り組みました。
※ 2023年度のインタビュー記事はこちら
合金触媒の表面における金属配置の最適化問題です。ユーザーが指定した金属の比率となるように表面モデルに金属種を割り当てます。割り当てた際に、合金が安定する(エネルギーが小さくなる)配置を求めます。
金属の種類×合金中の金属位置の2次元の決定変数(その種類の金属が存在する場合は1、しない場合は0)
決定変数のイメージ
| 金属の種類 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 金属a | 金属b | ・・・ | ||
| 金属位置 | 0 | q (0 or 1) | q (0 or 1) | |
| 1 | q (0 or 1) | q (0 or 1) | ||
| 2 | q (0 or 1) | q (0 or 1) | ||
| ・ | ||||
| ・ | ||||
| ・ | ||||
少数の教師データから作成した金属配置に対するエネルギー予測式(クラスター展開を用いて回帰)の最小化(最安定な金属配置の探索)
一番苦労したことは、表面に着目したことにより、計算規模が大幅に増加したことです。昨年度は、結晶構造が無限に連なっているような状況を想定していたので、結晶構造の対称性を活用することで最適化の計算を効率的に行うことができました。しかし、今年度は表面のみに着目したので、境界が発生し、それぞれの金属位置を表面からの距離に応じて異なるグループとみなす必要が生じました。これにより、昨年と比べて、目的関数であるエネルギー予測式に用いる変数と必要な教師データの数が多くなり、膨大な計算コストが必要となってしまいました。
この課題に対応するために、量子アニーリング・イジングマシンを活用したブラックボックス最適化(QA-BBO)を活用しました。具体的には、クラスター展開による回帰を行う際に使う変数の選択をQA-BBOで行い、150個程度の変数の中から30~50個を選択してモデルを構築しました。変数の数を削減することでモデルの精度は落ちるのかと思っていたのですが、逆にモデルの精度が上がって大変驚きました。すべての変数を使った方が精度は良くなるという先入観がありましたが、必要な変数だけを適切に選択することでモデルの精度が上がるというのは、この試行錯誤から得た重要な知見となりました。
対称性の崩れに伴い、昨年度のコードから金属位置の扱い方などを大幅に変更する必要がありました。手元で簡単な実験を行う中で、コード中に現れる係数に一定の法則性を見出し、それを活用して効率的な実装ができたときはとても嬉しかったです。また、今回開発したツールは、取り扱う金属の種類が増えても汎用的に対応できるよう設計しており、意図通りに動作したときには大きな達成感がありました。
また、全体を通して、Fixstars
Amplifyのnum_solvesを活用した効率的な最適化アルゴリズムの開発や、QA-BBOを用いた変数選択など、自らの課題を最先端のツールを使いこなして乗り越えていく過程は非常に刺激的で楽しいものでした。Fixstars
Amplify社の方にもいろいろとご相談させていただき、大変助かりました。QA-BBOについては、テスト公開中のAmplify-BBOpt(QA-BBO向けのライブラリ)を利用しましたが、複雑なアルゴリズムの実装が驚くほど簡単に行えた点に感動しました。今後、正式版のリリースでさらに使いやすくなるとのことなので、とても楽しみにしています。
論文の公開やツールのGitHub公開を計画しています。準備が整ったら広く一般に公開して、世界中の触媒研究者の方に使ってもらえるようにしていきたいと思っています。
一見すると組合せ最適化問題に見えない課題も定式化できる、というようなことが往々にしてあるのが組合せ最適化の面白さだと感じています。今回の未踏ターゲット事業においても、他のチームの方々がそれぞれの課題に応じて様々な定式化を提案されており、非常に興味深かったです。今後も、これまで思ってもいなかったような分野での応用が広がっていく様子を目にするのが楽しみです。
*本記事の掲載内容は全て取材時の情報に基づいています